
後見制度を活用する上でよく聞く「後見登記」についてよくわからない方も多いのではないでしょうか?
自分が後見人である事実を証明する際に必要となる後見登記制度。
この後見登記制度を理解し、後見制度を円滑に利用したいものです。
事実、後見登記は、後見制度を利用するために必要なことです。
なぜなら、後見登記ができていることで、後見人であることを証明する書類を発行でき、被後見人に代わって様々な身上監護契約や財産管理手続きるからです。
また、後見人ではない方にとっても、資格登録等の際に後見登記されていないことを証明する書類を求められることがあるため、後見登記について理解しておくことが必要です。
このように、後見人であること・後見人でないことを証明するために欠くことのできないのが後見登記です。
本記事では、後見登記についてわかりやすく解説します。
後見登記を理解し、円滑に必要な手続きを行えるようにしていきましょう。
目次
1.成年後見登記制度とは?
(1)後見登記とは?
後見登記制度とは、後見人の方にとっては、正式に自分が後見人である事実を証明する際に必要となる制度です。
成年後見の登記は、後見制度(法定後見制度・任意後見制度)の適用を受ける場合に、被後見人・後見人の氏名、住所、後見人の権利の範囲など、その後見に関する内容が正式に登録・開示されます。
逆にいいますと、ある人が後見人として、被後見人の方の財産管理や身の回りの代理行為を行うためには、正式に後見登記がされていなければならないということになります。
そして、自分が後見人であるという事実を証明しなければいけない場合には、法務局で登記事項証明書という書類を発行してもらいます。
例えば、被後見人の方の不動産を売却するような場合や、被後見人に代わって介護施設の契約をするような場合にこの証明書の提示を求められるわけです。
また、この制度は、これから成年後見制度を利用しようとしている方(後見人を必要としている方)にとっては、まだその方に後見人がついていない事実を証明する際にも利用することになる制度です。
この場合には、法務局で登記されていないことの証明書という書類を発行してもらい、後見開始の申立てを行う際に申立書と一緒に家庭裁判所に提出します。
(2)任意後見・法定後見の登記方法の相違点と共通点
| 任意後見制度 | 法定後見制度 | |
| はじめの登記 | 公証人が行う | 家庭裁判所が行う |
| 変更の登記 | 後見人が行う | |
| 終了の登記 | 後見人が行う | |
また、任意後見制度と法定後見制度では登記手続きに、次のような異なる点と共通する点があります。
①相違点
まず、任意後見と法定後見では、その後見がはじめに登記されるタイミングが異なります。
はじめに登記されるタイミングは、任意後見では任意後見契約が締結された時点、法定後見では、家庭裁判所が後見人を選任した時点となります。
任意後見制度の場合は公証役場の「公証人」が、法定後見制度の場合は「家庭裁判所」がそれぞれ後見登記を行います。
ですから、はじめの登記は、どちらも後見人の方が行わなければならない手続きではないということになります。
②共通点
それから共通する点としては、「変更登記」と「終了登記」の2つの登記があります。
「変更登記」とは、後見契約締結時や後見開始時に登記された当初の情報が変更された場合、例えば、後見人の住所など、登記内容が変更になった場合に必要な登記です。
「終了登記」は、被後見人の方が亡くなり、後見を終了する場合に必要な手続きになります。
そして、これら2つが、後見人の方が自分で行う必要のある後見登記手続きです。
これらの具体的な内容については次の章で解説しますので、しっかりと抑えておきましょう。
(3)登記されている場所は?
後見登記の内容は、東京法務局のコンピュータに全国のデータが収められています。
ただし、証明書の申請や交付については、全国各地の法務局窓口で行えます。
2.後見人が行う必要のある登記申請
上述のとおり、後見人が行う必要のある登記は「変更登記」と「終了登記」です。
では、それぞれ登記の方法を具体的に見てみましょう。
| 変更登記 | 終了登記 | |
| 登記が必要な場合 | 登記事項の内容に変更があった場合 | 被後見人の死亡や判断能力の回復により後見を終了する場合など |
| 必要書類 | ・変更登記申請書 ・変更の事実を示す書類 |
・終了登記申請書 ・終了の事実を示す書類 |
| 申請方法 | 東京法務局で窓口申請、または郵送 | 東京法務局で窓口申請、または郵送 |
| 申請できる人 | ・後見人 ・被後見人の親族 ・その他の利害関係者 |
・後見人 ・被後見人の親族 ・任意後見契約を結んでいる両者とその親族 ・その他の利害関係者 |
| 費用 | 収入印紙1400円分 | なし |
(1)変更登記
次のいずれかの場合には変更登記が必要となります。
●被後見人、後見人、後見監督人など、登記されている人の住所・氏名・本籍に変更があった場合
●後見人、後見監督人が死亡、破産した場合
①登記に必要な書類
<申請書>
●変更登記申請書
<変更した内容別・必要書類>
●住所に変更があった場合/住民票の写しか戸籍の附票(役所で取得します)
●氏名・本籍に変更があった場合/戸籍謄本の原本(役所で取得します)
●後見人が亡くなった場合/死亡の事実がわかる戸籍謄抄本(役所で取得します)か死亡診断書(病院で取得します)
●後見人が破産した場合/破産決定正本(破産時に取得済みです)
②申請方法
申請方法は、窓口での申請と郵送での申請が可能です。
申請は、東京法務局・後見登録課(〒102-8226 東京都千代田区九段南1-1-15九段第二合同庁舎4階)でのみ受け付けています。
③申請ができる人
このページでは、後見人がすべき登記としてご紹介していますが、変更の登記は後見人以外の以下の人にも登記が認められています。
●被後見人の親族
●その他の利害関係者
④申請に必要な費用
変更登記には、一件の変更申請につき1400円分の収入印紙が必要となります。
(2)終了登記
被後見人の方が亡くなった場合には、終了の登記が必要になります。
また、任意後見契約が解除になった場合にも同様に終了の登記が必要です。ちなみに、任意後見契約が解除になる場合とは次のような場合をいいます。
●契約者どうしが合意して解除した場合
●契約者どちらかが一方的に解除した場合
●契約者どちらかが破産した場合
●任意後見人が認知症などにより判断能力が低下し、後見人が必要となり、別の後見の被後見人になった場合
①登記に必要な書類
<申請書>
●終了登記申請書
<終了の理由別・必要書類>
●被後見人死亡の場合/死亡の事実がわかる戸籍謄抄本(役所で取得します)か死亡診断書(病院で取得します)
●後見開始前の任意後見契約解除の場合/
・合意解除の場合:合意解除の意思を記載し、公証人の認証を受けた書面の原本または謄本(公証人に認証を受けた際に取得済みです)
・一方的解除の場合:一方的解除の意思を記載し、公証人の認証を受けた書面の謄本と、謄本を受け取った際の配達証明(公証人に認証を受けた際に取得済みです)
●後見開始後の任意後見契約解除の場合/合意の解除または一方的解除の意思表示を記載した文書、家庭裁判所の審判書、審判書の謄本と確定証明書(契約解除の際に取得済みです)
●任意後見契約を結んだ両者のいずれかが破産した場合/破産決定正本(破産時に取得済みです)
●任意後見人が認知症などにより判断能力が低下し、被後見人の立場として後見が開始されてしまった場合/後見開始の審判書謄本と確定証明書(後見開始時に取得します)
②申請方法
申請方法は、窓口での申請と郵送での申請が可能です。
申請は、東京法務局・後見登録課(〒102-8226 東京都千代田区九段南1-1-15九段第二合同庁舎4階)でのみ受け付けています。
③申請ができる人
このページでは、後見人がすべき登記としてご紹介していますが、終了の登記は後見人以外の以下の人にも登記手続きが認められています。
●被後見人の親族
●任意後見契約を結んでいる両者とその親族
●その他の利害関係者
④申請に必要な費用
終了の登記には費用はかかりません。
3.証明書の発行手続き
法務局で発行している証明書には、「登記事項証明書」と「登記されていないことの証明書」の2種類になります。
| 登記事項証明書 | 登記されていないことの証明書 | |
| 必要になる場合 | 後見人が被後見人の代理行為を行う場合など | 後見開始の申立てを行う場合など |
| 請求方法 | ・必要書類を窓口へ持参/郵送 ・オンライン請求 |
・必要書類を窓口へ持参/郵送 ・オンライン請求 |
| 必要書類 | ・登記事項証明書・申請用紙 ・身分証明書、委任状など |
・登記されていないことの証明書、申請用紙 ・身分証明書、委任状など |
| 請求先 | ・窓口請求は全国の法務局 ・郵送は東京法務局のみ |
・窓口請求は全国の法務局 ・郵送は東京法務局のみ |
| 請求できる人 | ・登記されている当事者(被後見人、後見人、後見監督人) ・被後見人の4親等内の親族 ・上記から委任された人 |
・証明対象となる人本人 ・本人の4親等内の親族 ・上記から委任された人 |
| 費用 | 窓口/郵送:550円 オンライン(紙の証明書):380円 オンライン(電子データ):320円 |
窓口/郵送:300円 オンライン(紙の証明書):300円 オンライン(電子データ):240円 |
(1)登記事項証明書
登記事項証明書は、後見人が被後見人に代わって何らかの取引を行う際に、必要となることが多い証明書です。
証明書の請求方法は次のとおりです。
①請求方法
必要書類を法務局の窓口に持参するか、郵送します。オンラインで請求することもできます。
窓口へ持参する場合には、全国の法務局で受け付けていますが、郵送の場合は、東京法務局・後見登録課(〒102-8226 東京都千代田区九段南1-1-15九段第二合同庁舎4階)でのみの受け付けとなっています。
②申請ができる人
登記事項証明書の申請は、以下の人に申請が認められています。
●登記されている当事者(被後見人、後見人、後見監督人)
●被後見人の4親等内の親族
●それらの人から委任された人
③必要書類
●登記事項証明書・申請用紙
●添付書類
・登記されている当事者が申請する場合
本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカード等)
・被後見人の4親等内の親族が申請する場合
4親等内の親族であることを証明する戸籍謄本
・被後見人か後見人から委任されて請求する場合
委任された人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカード等)と委任状
・被後見人の4親等内の親族から委任されて請求する場合
委任された人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカード等)、委任した人が4親等内の親族であることを証明する戸籍謄本と委任状
④申請手数料
登記事項証明書の交付には、1通あたり以下の金額の収入印紙が必要になります。
| 窓口・郵送での請求 | 550円 |
| オンライン請求(紙の証明書) | 380円 |
| オンライン請求(電子データ) | 320円 |
(2)登記されていないことの証明書
登記されていないことの証明書とは、その人が後見人や被後見人としてまだ登記されていないことを証明するときに必要な証明書です。
この書類は、主に後見開始の申立ての際に提出する必要がある書類になります。
証明書の請求方法は次のとおりです。
①請求方法
必要書類を法務局の窓口に持参するか、郵送します。オンラインで請求することもできます。
窓口へ持参する場合には、全国の法務局で受け付けていますが、郵送の場合は、東京法務局・後見登録課(〒102-8226 東京都千代田区九段南1-1-15九段第二合同庁舎4階)でのみの受け付けとなっています。
②申請ができる人
登記されていないことの証明書の申請は、以下の人に申請が認められています。
●証明対象となる人本人
●本人の4親等内の親族
●それらの人から委任された人
③必要書類
●登記されていないことの証明書・申請用紙
●添付書類
・本人が申請する場合
本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカード等)
・本人の4親等内の親族が申請する場合
4親等内の親族であることを証明する戸籍謄本
・本人から委任されて請求する場合
委任された人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカード等)と委任状
・本人の4親等内の親族から委任されて請求する場合
委任された人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカード等)、委任した人が4親等内の親族であることを証明する戸籍謄本と委任状
④申請手数料
登記されていないことの証明書の交付には、1通あたり以下の金額の収入印紙が必要になります。
| 窓口・郵送での請求 | 300円 |
| オンライン請求(紙の証明書) | 300円 |
| オンライン請求(電子データ) | 240円 |
4.まとめ
以上のような後見登記の知識については、後見制度を利用する方には必須だといえるでしょう。
最低限の知識はしっかりと抑えておき、いざ必要となった際にすみやかに手続きを行って、無用のトラブルを避けるように活用していただければ幸いです。

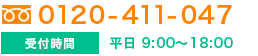


コメント